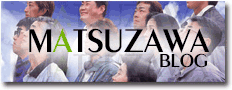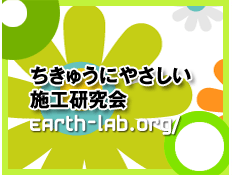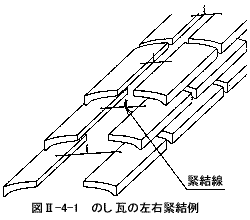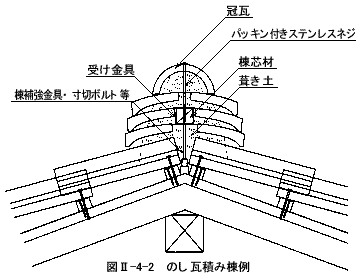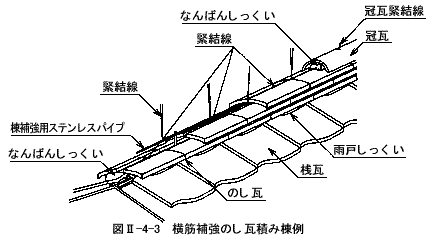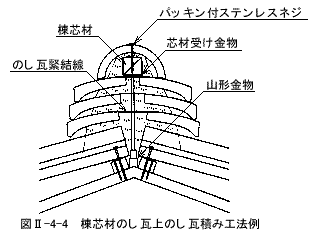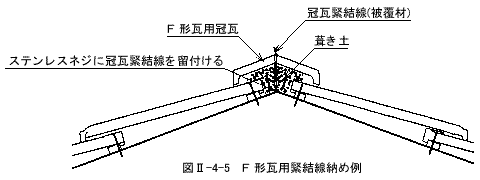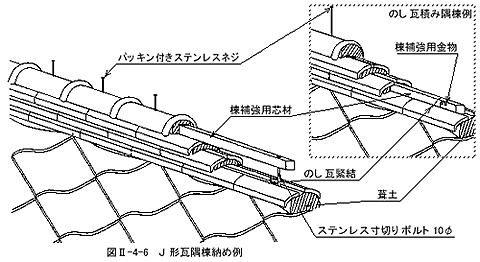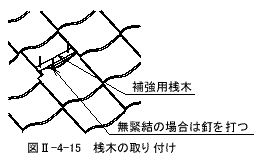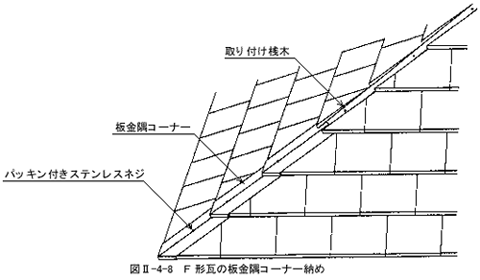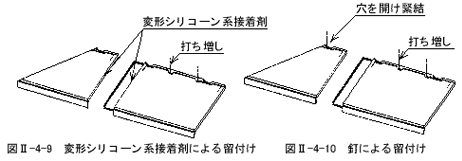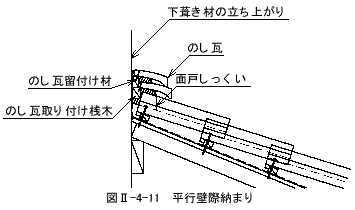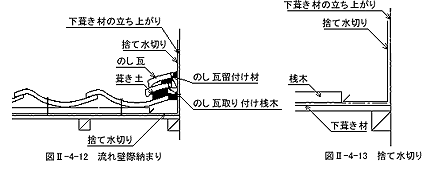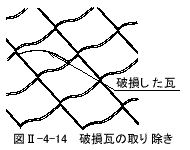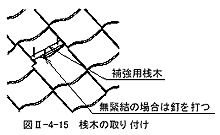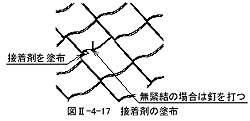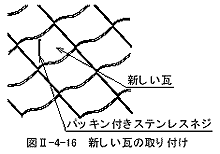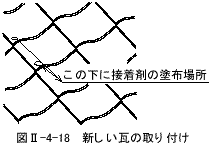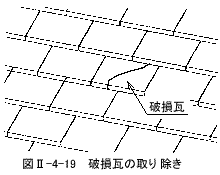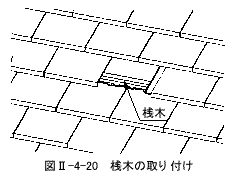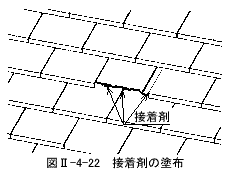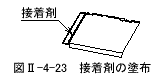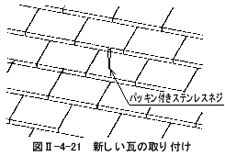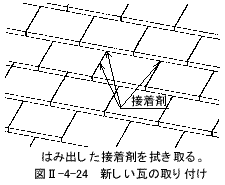マツザワ瓦店では、安心かつ確実に施工を行う為に、施工手順書に基づいて施工を行っております。
下葺き材を下地に留付ける場合、通常タッカーを使用してステーブルを打ち留付ける。ただし打ち込み不良で漏水の可能性があるので注意を要する。打ち込み不良の原因は、野地板が堅い場合にステーブルが挫屈するため発生する。この場合、金槌等で打ち増しする。野地板が柔らかい場合はステープルがめり込み亀裂が生じる。この場合は、シングルセメント等で亀裂を埋める等の処置を行う必要がある。 ステープルを使用しない方法は、接着工法、釘にシール用パッキンを組み合せた方法がある(止水性の向上)。 天然素材である木材を薄く削いだ物や、樹皮などの透湿性のある下葺き材が昔から使用されている。近年透湿性のあるシートも使用されている。 |
||||||||||||||||||||
桟木の取り付け方法は、下地により留付け方法が異なるので、最適な留付け材を使用し十分な強度を確保すること。円弧形状の意匠を持つ屋根面が設計され瓦を葺く場合の注意点は、瓦から漏水があった場合、下葺き材上の水を早く軒まで導く必要がある。解消法は、桟木の横継ぎ手は必ず50mm程度のすき間を取り、水が流れる道をつくる。すき間の位置は、円弧状の屋根面で水を流し流跡線や水管の位置を確認し決定すること。 |
||||||||||||||||||||
瓦緊結用釘の選定について、いぶし瓦の緊結には銅、黄銅の釘を使用すると腐食が進むのが早いので使用しない。又、桟瓦の釘穴径が小さい場合、瓦と釘の摩擦や結露でステンレス製の釘も、腐食の可能性が大きいので釘の周辺に十分な空間が必要である。 釘の軸部形状について、スクリュー形状は長期間引き抜きカが維持できない。スクリュー回転留め形状は下葺き材に釘軸部以外に空間ができる可能性があるので、漏水に注意を要する。リング形状については、長期間引き抜きカは維持できるが打ち込み時に大きな力が必要となるので施工時の瓦破損に注意を要する。 ネジの選定については、ステンレスを使用すること。ネジに使用するパッキンは耐候性、耐亀裂性ある素材とする。ネジを締め付けるとパッキンが飛び出したり、少しの傷でも割れるものがあるので選定には注意を要する。ネジ軸部先端形状については、先割れ等の加工が施されている場合は桟木の繊維を引っ掛けた状態で下葺き材を貫通するために必要以上の傷を付け漏水の原因となる可能性があるので注意を要する。 桟瓦の桟山から野地板を貫通して野地真にネジが出るような留付けを行う場合、ネジ軸部が熱架橋となりネジに結露の恐れがあるので注意を要する。釘の場合についても同様の現象が起きるので注意を要する。 ステンレスネジと異なる金属が接合される場合、どちらかに電気絶縁処理を施し電気的腐食を防止すること。緊結用鋼線をステンレス釘に留付ける場合も同様で、被覆銅線を使用してステンレス釘に留付ける方法を行うこと。 ネジ、釘、金物に使用するステンレスは通常SUS304製とするが、海岸等で塩が影響してネジ、釘を腐食させる場合には、SUS304に特殊な表面処理を施したり、高純度高Cr-高Mo鋼を検討する必要がある。SUS410・430製については耐腐食性が劣るので桟瓦の留付けや暴露する補強等に使用するのは望ましくない。 |
||||||||||||||||||||
瓦用接着剤にシリコーン系の材料を使用すると、施工方法によっては接着剤中に含まれるシリコーンオイル等が雨水等で流出し、瓦の表面に吸着され、シリコーンオイル等がほこり等の吸着材料となる。シリコーンオイル等は瓦の表面に吸着されると石鹸や溶媒で拭いても除去するのは難しいので、汚染した瓦を新しい瓦に交換する方法しかない。 汚染した瓦を放置するとほこりが吸着され、かびが発生する等、屋根の美観が著しく損なわれることがあるので、シリコーン系接着剤は使用場所及び塗布箇所に注意を要す。オイル汚染を少なく、また、無くしたい場合には変成シリコーン系の接着剤を使用することが望ましい。ただし、変成シリコーン系接着剤の中にもシリコーン系接着剤より少ないがオイル状物質が流出するものもあるので注意を要する。尚、変成シリコーン系接着剤はシリコーン系接着剤に比べ若干耐候性が劣るので暴露状態で使用する場合には接着剤の表面に塗装が必要な場合もある。 |
||||||||||||||||||||
(1)J形瓦 使用する桟瓦の幅、働き長さ寸法を確認後、割付けや墨だしを行うこと。瓦の持っている働き寸法以上の割付は厳禁である。 (2)S形瓦 J形瓦に比べ働さ長さ方向の重ね寸法が少ないので働き長さ寸法はなるべく小さく、横働きもメーカー表示よりも大きくならないようにする必要がある。2次防水として下茸材を2重にしたりグレードアップしたものを考える必要もある。 (3)F形瓦 J形、S形瓦と同等であるが、一枚あたりの露出面積が大きいので全数緊結以外の補強方法を十分に検討すること。特に陸棟や隅棟周辺の被害が過去に多く発生したのでマニュアルを熟知し工事を行うこと。 (4)棟の施工 棟の施工は、特に耐震を要求されるので棟補強金物等をもちいてしっかりと下地に固定する。のし瓦は左右を緊結線で留付ける。冠瓦は棟芯材にパッキン付きステンレスネジで留付ける等、地震、台風等で被害の無い棟を作ることが責務である。
(5)壁際の施工
谷についても夜露等に含まれる酸性物質などで腐食の被害が多く発生する。対策は谷縁瓦の水滴部にテープを貼るなどが考えられる。 |
||||||||||||||||||||
桟瓦の破揖による交換は、破損瓦を取り除き新しい瓦と交換する緊緒方法はパッキン付きステンレスネジで桟山から留付ける方法と接着剤による接着方法がある。 (1)J形瓦の補修
いぶし瓦に接着剤を使用する場合、炭素層のため十分接着できない場合があるので、いぶし部分をはく離させて接着することが望ましい。接着剤は変成シリコーン系の弾性があるものを使用する。シリコーン系を使用すると可塑剤やシリコーンオイル等が雨水等で溶出し瓦の表面が汚染することがある。また、エポキシ系やポリ酢酸ビニル系は使用不可である。 (2)F形瓦の補修
|
||||||||||||||||||||
| 上記方法で修理が出来ない瓦もあるので、瓦製造者の修理方法に従うこと。 | ||||||||||||||||||||